
【受付時間】 9:00-18:00(平日) 9:00-13:00(水・土)
【休診日】 日曜、祝日、水曜午後、土曜午後
(お盆)8月13~15日、(年末年始)12月29日~1月4日
一般歯科、小児歯科、予防歯科、ミラクルデンチャー
【受付時間】9:00-18:00(平日) 9:00-13:00(水・土)【休診日】日曜、祝日、水曜午後、土曜午後
(お盆)8月13~15日、(年末年始)12月29日~1月4日
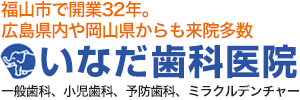

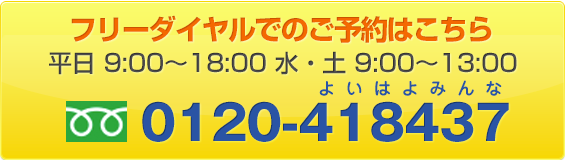
分子栄養学について三石巌先生や藤川徳美先生の著書を中心に勉強中です。歯周病に関連するこれまでの知識をいったんまとめてみたいと思います。今回は治療に関しては割愛させていただきます。
歯周病治癒に関して、今回は「分子栄養学から見た栄養摂取」について考えてみたいと思います。
歯周病は歯周病菌が繁殖して炎症を起こし、歯を支えている歯槽骨を溶かします。これに対抗するため十分なタンパク質とカルシウム及びビタミンCが必要になります。
ストレスには精神的ストレスと物理的ストレスがあります。精神的ストレスは例えば人間関係の悪化、大切な人の喪失、離婚、引っ越し、病気など、物理的ストレスには外傷、手術などいろいろありますが、そのどちらも、体の中ではタンパク質、カルシウム、ビタミンC、ビタミンEが大量に消費されます。
従って、それらの栄養素を十分補充しなければ、いくら歯科治療をしても改善されないし、場合によっては悪化してしまいます。手術を予定されている方は術前に上記栄養素を補充しておくといいです。
歯肉の出血は創傷であり、ビタミンCとタンパク質が充足すれば出血しなくなります。
コラーゲンはタンパク質なのです。
細菌が出す菌毒にもビタミンCが有効です。
歯周病菌にもビタミンCが効果を表すと思われます。
ビタミンCを多く含む食品:レモン、イチゴ、ミカン、柿、パセリ、トマト、ブロッコリー、ピーマン、サツマイモ、番茶
ビタミンEを多く含む食品:アーモンド、小麦胚芽、大豆、落花生、ウナギ、シジミ、カツオ、アユ
タンパク質を多く含む食品:肉(牛、豚、羊、鶏)、魚介類(魚、イカ、タコ、貝)、牛乳、卵、チーズ、大豆、豆腐、納豆、カマボコ、ちくわ
カルシウムを多く含む食品:
野菜―小松菜、モロヘイヤ、いりごま、菜の花、チンゲン菜、大根の葉、切り干し大根
魚介類―わかさぎ、干しエビ、オイルサーディン(いわし)、あゆ、ししゃも、ウナギかば焼き
大豆製品―焼き豆腐、生揚げ、がんもどき、木綿豆腐、凍り豆腐
乳製品―牛乳、スキムミルク、アイスクリーム、チーズ、ヨーグルト
サプリメントで簡単に摂取することが出来ます。お勧めします。
ホエイプロテイン、プロテインバー
ビタミンC
ビタミンE
カルシウム
現在推奨されている食事の栄養バランスは「糖質60%、脂質25%、タンパク質15%」だそうですが、これには特に根拠があるわけではなく、今の日本では調べると平均これぐらいですね、と言うデータです。
糖質はエネルギー源です。見渡せば糖質まみれ(糖質って美味しいですからね、白米ご飯、パン、メン類、お菓子など)で、私が小さい頃はどこに行くにも歩きか自転車、馬車もいました。車はお金持ちかお医者さん、運送会社のトラックしか通っていなかった。
今は便利になって、自家用車にエスカレーター、エレベーターに自宅配送、運動量は減って余った糖質はインシュリンホルモンによって脂肪に変換され体脂肪、皮下脂肪になります。肥満は消費しきれなかった糖質のせいなんです。
脂質は体の構成要素です。
細胞膜は脂質でできており、脳みその乾燥重量の約60%が歯質です。糖質が多すぎて脂質が少ないと神経伝達物質の誤作動により、例えばてんかんや原因不明の非定型歯痛、感覚異常症などになるのではないかと言われています。パーキンソン病などの神経難病にも関連していると思われます。
脂質には必須脂肪酸がありこれは必ず食事からとらなければいけません。
タンパク質は大切な体の構成要素です。骨格筋、臓器、爪、髪など体のほとんどがタンパク質で出来ています。骨もタンパク質とミネラルで出来ています。いろんなホルモンや酵素もタンパク質から作られます。
糖質制限食では「糖質10%、脂質60%、タンパク質30%」とも言われていますが、なかなか大変ですので、糖質を少し減らして減らした分タンパク質を増やすことから始めたらいいと思います。
その他、大事なことは疲れをためないことです。睡眠を十分とること、疲れないようにする。疲れたら休息を取ること。とても大事なことです。