
【受付時間】 9:00-18:00(平日) 9:00-13:00(水・土)
【休診日】 日曜、祝日、水曜午後、土曜午後
(お盆)8月13~15日、(年末年始)12月29日~1月4日
一般歯科、小児歯科、予防歯科、ミラクルデンチャー
【受付時間】9:00-18:00(平日) 9:00-13:00(水・土)【休診日】日曜、祝日、水曜午後、土曜午後
(お盆)8月13~15日、(年末年始)12月29日~1月4日
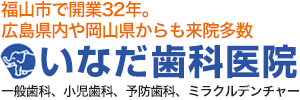

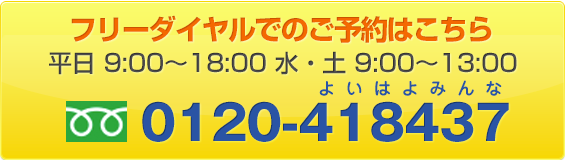
今週のお知らせは、糖尿病の治療に糖質制限食(高タンパク低糖質食)を取り入れて好成績を収めている京都高雄病院の理事長、江部康二先生のブログ「糖尿病徒然日記」からの記事です。
私は肥満と糖尿病一歩手前の状態から、江部康二先生の本を夫婦で読んで糖質制限を開始して体重は6~7Kg減少、低血糖症状(手指の震え、強烈な空腹感、眠気)も全くなくなりました。
人のエネルギー源は糖質由来のブドウ糖と脂質由来のケトン体です。一刻も休むことが許されない臓器(心臓など)はケトン体で動いています。糖質制限食はこのブドウ糖よりケトン体を優位なエネルギー源とするものです。
日本人は昔からコメを食ってきた人種だからと糖質制限に反対の立場の人がいますが、白米をたらふく食べれるようになったのは戦後です。私が白米を食べられるようになったのは大学に入ってからです。高校まで実家にいた時は、7分付きの米に麦が混ざっていました。白米は運動会などの時しか食べていません。また明治時代の陸軍は軍隊募集の時、白米をたらふく食べられるとの触れ込みでした。
江戸時代は、普通は雑穀や玄米が主食で白米が食べられるのは江戸住まいの大名などで、領地に帰ると玄米です。この頃の大名は江戸にいる時は白米を食べて脚気になり、領地に帰ると玄米を食べて健康になっていました。だから脚気のことを「江戸患い」と言っていました。
昔と今は生活スタイルが全く異なります。その生活に合わせた食事が必要になってきます。体を動かさなくても生活できる現代に、白米や小麦(ラーメン、うどん、パスタなど)などの糖質をたらふく食べていたら、余った糖質がインスリンによって脂肪に替えられて太ってしまい、場合によっては糖尿病になります。タンパク質や脂質は太らないと言うことが栄養学で分かってきているのです。さあ、やっと脂質由来のケトン体の出番です。
以下引用始め
こんにちは。
「ケトン産生食は心血管関連死亡を増やすことなく全死亡を減少させるポテンシャルを持っている(The ketogenic diet has the potential to decrease all-cause mortality without a concomitant increase in cardiovascular-related mortality)」
https://www.nature.com/articles/s41598-024-73384-x
というタイトルの論文がScientific reports誌に掲載されました。
(Sci Rep 2024; 14: 22805)。
以前から、私達糖質セイゲニストの医師達(江部、夏井医師、宗田医師、清水医師など)は「血中ケトン体が高値でも、インスリン作用が保たれている限り、それは生理的ケトーシスであり、安全である」と主張してきました。
例えば「断食(絶食療法)」「小児ケトン食」「スーパー糖質制限食」などがそれに相当します。」高雄病院では、1999年からスーパー糖質制限食を導入しています。
一方、特に日本では、「糖尿病ケトアシドーシス」というICU管理が必要な病態があることを理由に、ケトン体そのものはが悪であるように考えている医師が多いのです。しかし糖尿病ケトアシドーシスは、インスリン作用が保たれていないときだけに発症する特殊な病理的状態であり、安全な「生理的ケトーシス」とは全く異なる状態です。
欧米では、近年、ケトン体に肯定的な論文が多数発表されています。まとめれば「心・腎・脳保護作用」があり「慢性炎症予防効果」もあるということになります。これらを受けて、日本でもケトン体に対して肯定的な立場を取る医師が少しずつ増えていますが、残念ながらまだ少数派です。
今回、記事に取り上げた論文は、2001~18年にかけて実施された9回の米国民健康・栄養調査(NHANES)のデータを使用して、中国・上海交通大学の研究者らが解析したものです。
計9万1,351人のデータから、年齢、食事記録欠損、心血管疾患記録欠損などを除外して4万3,776人(49.4±18.1歳、女性48.3%)のデータを解析に使用しました。平均フォローアップ期間9.1年の間に、6,054人(13.8%)が死亡し、うち心血管疾患関連死亡は1,533人(3.5%)でした。結論としては「ケトン比が高い人ほど全死亡リスクが低い」であり、ケトン体高値が、おおいに有益であることを示しました。私達、糖質セイゲニストにとって、とても嬉しい結論の論文でした。
江部康二
以上引用終わり