
【受付時間】 9:00-18:00(平日) 9:00-13:00(水・土)
【休診日】 日曜、祝日、水曜午後、土曜午後
(お盆)8月13~15日、(年末年始)12月29日~1月4日
一般歯科、小児歯科、予防歯科、ミラクルデンチャー
【受付時間】9:00-18:00(平日) 9:00-13:00(水・土)【休診日】日曜、祝日、水曜午後、土曜午後
(お盆)8月13~15日、(年末年始)12月29日~1月4日
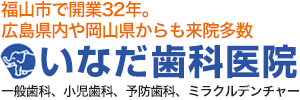

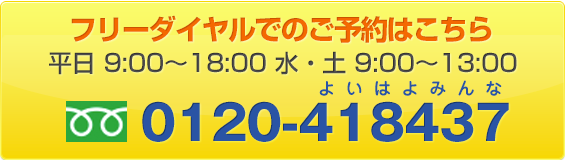
歯に付着するむし歯菌・歯周病菌を除去することで
を予防します。
歯全体をクリーニングしてマウスピースに除菌薬剤を塗布、歯に装着して5分間除菌。むし歯菌・歯周病菌は限りなく0に近づきましたが複雑に並んだ歯の周りでは残念ながら0ではありません。
1匹の菌が30分で1回分裂して増殖し14時間で10万匹になります。このまま放っておくと元の木阿弥です。効果を持続させる為にホーム除菌(家庭での除菌)が必要となります。
1日の歯みがきのうち1回、ていねいに歯みがきをした後マウスピースに除菌薬剤を塗布、歯に装着して5分間除菌します。これを7~10日間続けます。
経過観察。再度歯全体をクリーニングしてマウスピースに除菌薬剤を塗布、歯に装着して5分間除菌
上記を1クールとします。
1クールで効果は2カ月から12カ月(1年)続きます。むし歯を予防でき、歯周病を予防、進行した歯周病では進行を止めることが出来ます。また改善もできます。歯原性菌血症による病気も予防できます。毎日継続することをお勧めします。
むし歯が進行して象牙質に達するとむし歯菌が歯髄(神経)の血管に侵入します、また歯周病菌は歯周病が進行して弱った歯肉の血管に侵入します。このようにむし歯菌や歯周病菌が血管に侵入して全身に運ばれることを歯原性菌血症と言います。歯原性菌血症が続くと細菌の害と細菌が産生する毒素によって次のような病気になると考えられています。
ガン、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、高血圧、関節リウマチ、脳脊髄膜炎、心内膜炎、血行性肺炎、急性虫垂炎、肝臓膿瘍、脾臓膿瘍、早産、低体重児出産、アルツハイマー型認知症
出来れば毎日1回はホーム除菌(ホーム3DS)を継続します。また良好な結果を維持していく為には日常の生活習慣を変える必要があります。炭水化物の食べすぎを改善(糖質制限食をお勧めします)砂糖の摂り過ぎに注意(WHO勧告1日25g、調味料を引くと20g)歯みがき・歯肉マッサージを丁寧に(場合により音波ブラシの活用)
費用:¥32.400(税込み、簡易版)
【初期人類は糖質の多い食事をしていた】
700万年前~150万年前:木の葉や果実やベリー類大きな種子や地下の根など植物性食物が主体でした
【人類は氷河期に入って肉食になった】
150万年前~3500年前:狩猟や肉食獣の食べ残しや魚介類など動物性の食糧が増えてきます。少なくとも150万年前くらいから農耕が始まる1万年前くらいまでは、低糖質・高蛋白食であったことになります。各地に貝塚があります。
糖質の摂取量は現代人では1日250から400グラム程度ですが、狩猟採集時代の糖質摂取量は1日10から125gと推定されています。
【農耕が始まって高糖質食に適応するように進化しているが】
3500年前~150年前:日本において農耕が本格的に行われるようになったのは稲作が伝来した弥生時代に入ってからで、今から3000年から3500年くらい前と言われています。
特に近年のような単純糖質が多くグリセミック指数の高い(血糖値を上げやすい)食事には人間は適応する十分な時間を経ていないということです。
【精製した糖質の摂取に現代人は適応できていない】
150年前~現在:問題は、産業革命以降の急速な工業化と、近代における精製した単純糖質の摂取が増えたことです。単純糖質は殆ど糖質で出来上がっている食品で、白米、小麦粉などで代表は砂糖です。
砂糖や異性化糖(でんぷんを酵素などで処理して作ったグルコースとフルクトースの混在した糖)は近代に入るまで人類の食事には無かった食品です。この単純糖質の摂取に対して人間は遺伝的にほとんど無防備な状態です。
精製した糖質の摂取と運動量の減少が肥満や糖尿病、虫歯や歯周病、メタボリック症候群など多くの病気を引き起こしているのは明らかです。このような食事と生活環境の変化が急激に起こったために、人類は適応できていないのが原因となっています。
チンパンジーの脳容積は400㏄程度で、現代人の成人男性の脳容積の平均は約1350㏄です。チンパンジーと同程度の脳容積しかなかった初期人類から、高度の知能をもった現生人類に進化する過程で脳容積は3倍以上に増えました。動物性の栄養素が増えたことが、人類の脳を大きく成長させ、知能の発達に大きく寄与したと言えます。
しかし、農耕が始まってから、成人の平均身長は減少しているという報告があります。また、骨粗しょう症や虫歯も増えています。そして、農耕が始まって人類の歴史の中ではじめて脳の重量が減少していることが報告されています。
現代人の脳容積は、2万数千年前までヨーロッパに存在したネアンデルタール人の脳容積より10%程度小さいことが明らかになっています。その理由としてタンパク質や不飽和脂肪酸の摂取量の減少が指摘されています。
現在の日本の食事では炭水化物、たんぱく質、脂質の3大栄養素の比率は炭水化物が60%を超えており、残りがたんぱく質、脂質になっています。糖質は炭水化物から食物繊維を引いたものです。
従って、炭水化物の中で糖質の多い主食(白米、パンやめん類、パスタなどの小麦粉製品)を少なくして食物繊維の多い炭水化物(葉物野菜など)が推奨されたんぱく質と脂質を増やすものです。
簡単に言うと主食と甘いおやつを減らして、その分おかずを増やして全体量は減らさないようにします。肉、魚介、卵、チーズなどは積極的に摂ります。
新型コロナウイルス感染症について、以前に花田信弘先生(口腔感染症研究の第1人者)の解説を取り上げました。それによれば、一旦ウイルス性肺炎が治まった後、(感染しても、まったく症状の出ない人もたくさんいます)二次的に細菌性肺炎を起こすというパターンが多いというデータが出ています。
つまり、ウイルス性肺炎は軽症なので、二次的な細菌性肺炎を予防すれば重症化しないと言うことです。細菌性の肺炎は血行性肺炎、誤嚥性肺炎があります。進行したむし歯のむし歯菌や、進行した歯周病の歯周病菌が毛細血管から侵入すると血行性の細菌性肺炎が起こりやすくなります。
また口の中がゴミ屋敷のような状態で誤嚥すると誤嚥性肺炎の危険性が高いのです。重症化を防ぐために定期的な歯科受診をお勧めします。
いなだ歯科医院