
【受付時間】 9:00-18:00(平日) 9:00-13:00(水・土)
【休診日】 日曜、祝日、水曜午後、土曜午後
(お盆)8月13~15日、(年末年始)12月29日~1月4日
一般歯科、小児歯科、予防歯科、ミラクルデンチャー
【受付時間】9:00-18:00(平日) 9:00-13:00(水・土)【休診日】日曜、祝日、水曜午後、土曜午後
(お盆)8月13~15日、(年末年始)12月29日~1月4日
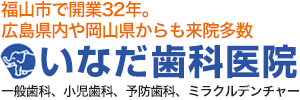

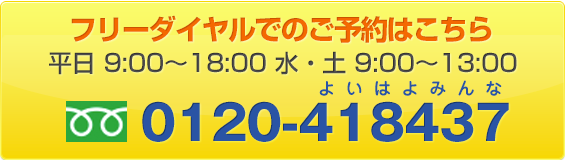
こんにちは。今回は、いわゆる長寿村について考察してみます。
まずは、以前は長寿村の代表と言われた棡原村(ゆずりはらむら)について検討してみます。棡原村はかつて山梨県北都留郡にあった村で今は廃止となっています。そして、現在では、単なる過疎の村であって、長寿村ではなかったことが明らかとなっています。以下は、長寿率と超高齢化率の定義です。
<長寿率と超高齢化率>
☆長寿率:65歳以上人口/全年齢人口(%)
☆超高齢化率:90歳以上人口/65歳以上人口(%)
長寿指標 全国(75) 秋田県(75) 沖縄県(75) 棡原村(77)
超高齢化率 0.92 0.55 2.46 0.90
長寿率 4.86 5.26 7.25 9.36
出典:松崎俊久・柴田博 老人科診療 1981:2:341
棡原村は、以前の長寿率でみると、9.36で全国平均の倍近くあって、一見長寿村のように見えますが、超高齢化率は0.90であって、全国平均レベルに過ぎません。この現象は、若者が都会に出て行った結果過疎化してしまった村で、高齢者比率が結果として多くなったということを意味していて、本当の長寿村ではなかったということを示しています。
これに対して沖縄は、超高齢化率が2.46で全国平均の2.67倍であり、本当の長寿であることを示しています。「沖縄の長寿のもっとも大きな要因は、日本全体がまだ肉不足にあえいでいた頃から
肉をよく食べ、また脂肪摂取量が全国の平均を1日5gくらい上回っていたことである。」「また冷蔵庫の普及の遅れた沖縄は、腐敗を防ぐためもあって油をよく使っていましたがその分、食塩摂取量は全国一少なかったのです。」と柴田博氏は、著書で指摘しています。
結局、沖縄の食文化は、長期間琉球王国として独立していて、日本の他の地域とは大きく異なっていたということが重要です。日本では仏教の伝来と普及により675年、天武天皇(飛鳥時代)が最初の食肉禁止令を発布しました。
この時禁止されたのは、牛・馬・犬・鶏の家畜と、猿の肉です。しかし、なぜか当時最も食された鹿や猪は禁止されませんでした。ともあれ、沖縄では仏教はほとんど普及しなかったため、肉食タブーという文化がそもそも存在していなかったので肉食文化が発達し、豚や山羊を常食していました。
この肉食文化や油の積極的摂取が、当時の沖縄の長寿におおいに貢献したと考えられ、糖質制限食の立場からも、おおいに納得がいきます。
☆☆☆
参考:長寿の嘘 柴田博著 2018年9月 株式会社ブックマン社
江部康二