60代 女性
作製用模型と作製されたミラクルデンチャー
最初に合わせる所をキーと言います。右上34口蓋がキーとなります。
ロックは最後に合わせる部分です。前歯を合わせて最後に左上5がロックになります。
ロックを合わせました。
ミラクルデンチャーが装着されました。
正面観です。黙っていれば入れ歯とは判りません。
実際の装着状態です。黙っていれば入れ歯とは判りません。噛み合わせの調整(これが一番大事)をして、歯肉にぴったり合う処置(裏層)をしたので約1時間かかりました。
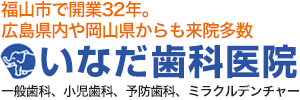

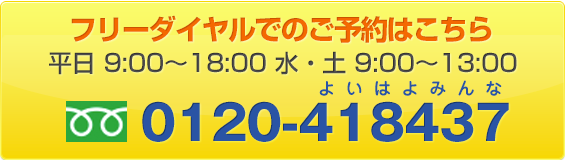
糖質制限食に関する新しい知見が発表されました。デンマーク・オーフス大学病院の最新研究よると炭水化物を控えること(糖質制限)で「脳の血流が劇的に改善する」ことが明らかになりました。
私は13年前から糖質制限を始めました。そのころ、食べる量と飲む量は変わらないのに少しずつ太ってきました。今思うと糖尿病になりかかっていたようです。糖質制限食は主食であるコメのご飯、パン、うどん、ラーメン、スパゲッティなどのめん類を減らして、減らした分量だけ肉類、魚介類、卵、チーズを増やす食事です。
実は、糖質、タンパク質、脂質の中で一番太るのは糖質だそうです。糖質はエネルギー源ですが食べ過ぎて使われなかった糖質はホルモンの働きによって脂肪に替えられ身につきます。タンパク質は体の重要な構成要素です。
脳みそを除いて体のほとんどがタンパク質で出来ています。爪、髪の毛、ホルモン、神経伝達物質などもタンパク質で出来ているので一番大事な栄養素です。脂質は脳みそや細胞膜に必要で、食べすぎると便の中に排出されるそうです。糖質制限を始めて半年もしないうちに体重は6~7kg減少し、ズボンも1サイズ細めのものがはけるようになり現在に続いています。
以下引用始め
糖質制限と聞くと、「ダイエットの一種」と思う人が多いかもしれません。
しかしデンマーク・オーフス大学病院(AUH)の最新研究では、炭水化物を控えることで「脳の血流が劇的に改善する」ことが明らかになりました。日々の献立から「炭水化物」を減らすだけで、脳のパフォーマンスが高まり、神経の働きを助ける重要なタンパク質まで増えるというのです。 これはもはや減量テクニックではなく、脳の健康を守る“戦略的食事法”と呼べるかもしれません。 では、その仕組みとは一体どのようなものなのでしょうか?
研究の詳細は2025年4月2日付で医学雑誌『The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism』に掲載されています。
Ketogenic diet raises brain blood flow by 22% and BDNF by 47% in new studyhttps://www.psypost.org/ketogenic-diet-raises-brain-blood-flow-by-22-and-bdnf-by-47-in-new-study/
A 3-Week Ketogenic Diet Increases Global Cerebral Blood Flow and Brain-Derived Neurotrophic Factorhttps://doi.org/10.1210/clinem/dgaf207
生物学に興味のあるWebライター。普段は読書をするのが趣味で、休みの日には野鳥や動物の写真を撮っています。
ナゾロジー 編集部Nazology Editor
目次
通常の食事では、脳は主にブドウ糖(グルコース)をエネルギー源としています。しかし炭水化物の摂取量が大幅に減ると、身体は「ケトーシス」と呼ばれる代謝状態に入り、肝臓が脂肪を分解して「ケトン体」という物質を生成します。
これらのケトン体は血液脳関門を通過し、代替エネルギー源として脳に供給されます。こうした食事を「ケトジェニック食」と呼びます。ケトジェニック食は具体的に、炭水化物の摂取を大幅に減らし、代わりに脂肪を多く摂取するという食事法です。
これにより、体が糖の代わりに脂肪を燃やし、ケトン体という物質をつくって、これがブドウ糖の代わりに脳のエネルギー源として働くのです。ケトーシス状態になることで、体は効率よく脂肪を分解し続け、血糖値の急上昇や急降下を避けることができます。それにより、集中力や精神的な安定感が高まるともいわれています。
Credit: canva
では、どんなものを食べればケトーシスに入れるのでしょうか?一般的に、ケトジェニック食のカロリー比は、脂肪が70~75%、タンパク質が20%、炭水化物が5~10%程度となっています。このような食事によって、脂肪の酸化とケトン体の産生を促すことが狙いです。
例えば、ご飯やパン、麺類などの炭水化物は抜いてしまって、代わりに肉・魚・野菜、ナッツ類、チーズ、卵などを増やします。またケトジェニック食では、砂糖を含むスナックやパン菓子なども完全に抜きます。研究チームは今回、ケトジェニック食が脳の血流にどのような作用を与えるかを実験しました。
対象となったのは、50〜70歳の認知機能に問題のない健康な成人11人。彼らは3週間ずつ、通常のバランス食とケトジェニック食を体験し、その効果を比べられました。各食事期間の終了時には、脳の血流をPETスキャンで測定し、同時に血液検査も実施されました。研究結果は驚きの連続でした。
まず、ケトジェニック食を3週間続けた被験者は、血液中のケトン体の濃度が、通常食に比べて12倍以上に増加しました。これはしっかりとケトーシスに入った証拠です。そして、最も注目すべきは脳の血流量。なんとケトジェニック食の期間中は、脳全体の血流が平均で22%も増加していたのです。
これは脳への酸素や栄養の供給がそれだけスムーズになっていたことを意味します。さらに神経細胞の成長や可塑性(柔軟性)を促すタンパク質「BDNF(脳由来神経栄養因子)」の血中濃度も47%増加していました。このタンパク質は、記憶力や学習能力を支える「脳の肥料」とも言われており、認知症の予防にも関係しています。
健康な人にも脳機能改善の可能性
これまで、ケトジェニック食はアルツハイマー病や軽度認知障害の人に効果があるとされてきました。
しかし今回の研究では、まったく認知機能に問題のない健康な人においても、脳血流とBDNFが明確に増加することが確認されました。つまり、ケトジェニック食は「病気の治療食」ではなく、むしろ「脳を最適化する食事法」としての可能性を秘めているのです。この研究はまだ少人数で短期間の結果ですが、それでも「食事が脳にこれほど強く作用する」ことを改めて示した重要な報告です。
炭水化物を控え、脂質を主なエネルギー源とすることで、脳はより多くの血液を受け取り、より強く活性化される可能性があるのです。
もちろん、ケトジェニック食は万人向けではありません。医師の監修なく無理に実施することで何らかの問題が起きる可能性もあり、持病や体質によっては合わない人もいます。しかし脳の健康維持や集中力の向上を目指す人にとっては、選択肢の一つとして注目に値する食事法といえるでしょう。
以上引用終わり
私の仲間の一人はコロナの後遺症で味覚がなくなりました。私やほかの仲間から、亜鉛の話や具体的にカキ(牡蠣)がいいとか色んなアドバイスがラインでなされました。
2年半前、孫たちと食事をしてゲームなどで遊びました。そのあと孫がコロナにかかっていると連絡がありました。程なくして、熱は無いのですがなんとなく違和感を感じたので検査キットを買ってきて調べたところ、見事に陽性でした。
体調的には仕事は出来そうだったのですが、法律にのっとって4日ほど休診しました。2類から5類に変わって少し落ち着いてきても、まだ時々流行しているようです。最近やはり仲間の一人がコロナで入院したと報告がありまだまだ収束していないことを実感しました。
ちなみに、私はワクチンを打っていません。mRNAは役目を終えたら溶けてなくなると言われていましたが、人間の体は複雑で必ずそうなるとは限らないだろうと思っていました。(その後、2年経ってもmRNAが残っている症例報告などがありました。)しかもまだ完成品ではなく、本来なされるべき治験がなされていないのがどうしても納得できませんでした。自分はモルモットにはなりたくないと言う気持ちでした。
政府はワクチンを2回打ったら集団免疫を獲得してコロナは収束すると言っておきながら、前言を翻して3回目4回目と進むことになりました。当院のスタッフは真面目に打って副反応に耐えていましたが、3回目の時あるスタッフが「死ぬかと思った、もう2度と打たない」と言って、スタッフ全員それ以後打ちませんでした。今回のコロナについてはぜひとも検証をして同じような事態が起きた時に備える必要があると思っています。
亜鉛ですが、私はサプリメントで取っています。3~4年前に藤川徳美先生の栄養学に出会ってからプロテインをはじめとして数種類のサプリメントを取っています。それによって私の体調はビックリするほど良い状態に変わりました。
それでは、京都高雄病院の江部先生の「糖尿病徒然日記」の記事を転載します。
以下引用始め
因みにコロナ後遺症の味覚・嗅覚障害 ほとんどの患者が「亜鉛不足」
2025年02月07日 (金)
こんばんは。
2025年1月20日~26日 新型コロナの感染状況
(1医療機関あたり)
新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが、2023年5月8日(月)に「5類」に移行したことに伴い、新型コロナの感染状況を示すデータは、これまでの「全数把握」から、全国5000の医療機関からの報告をもとに公表する「定点把握」に変わりました。
全国の5000の医療機関の平均1日当たり入院患者数
2025年1月13日〜1月19日 5.62人
2025年1月20日〜1月26日 6.06人
新型コロナの流行は大分下火になっていたのですが、2024年~2025年の年末年始とまた少し増え始めていますので油断は禁物です。また、感染時の症状は軽くても、後遺症が長引くことがあるので要注意なのです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/ac4dd792a3f0f263b3948817fb4789f9686c1340
コロナ後遺症の味覚・嗅覚障害 ほとんどの患者が「亜鉛不足」
2/9(火) 16:05配信
2021年2月9日、ヤフーニュースに上記の記事が掲載されました。この味覚障害と嗅覚障害、若い世代を中心に長く続くようです。ハンドボール元日本代表の宮崎大輔氏は、昨年12月25日に呼吸困難となり、2時間ほど意識を失っていたそうです。39歳ですから、まだまだお若いですが、かなりの重症です。熱が出てすぐに味覚と嗅覚がなくなって、1ヶ月半経過してもまだ完全には治らないとのことです。
ヒラハタクリニック院長の平畑光一医師は 「血液検査をすると、ほとんどの後遺症患者で亜鉛が不足しています。亜鉛不足は以前から味覚・嗅覚障害の原因として知られており、コロナ後遺症でもそれが原因の可能性がある。実際に亜鉛のサプリメントを服用することで症状が改善する例も多く見られます。・・・」と述べておられます。
亜鉛は発育や成長を助けたり、インスリンを合成する際にも不可欠な微量ミネラルで、皮膚代謝や糖代謝、免疫にもかかわっています。高雄病院や江部診療所で、血中亜鉛の検査をすることがありますが、糖尿病では、過半数の人が亜鉛不足です。
特に、50代~60代以上の糖尿人は、ほとんどの人が亜鉛不足です。20代や30代の人は、亜鉛不足はまず見られませんので、年齢とともに、亜鉛の吸収障害が出てくるものと思われます。
亜鉛が不足すると免疫にも影響して、易感染性となります。風邪をひきやすい人は一度亜鉛不足をチェックするとよいでしょう。ファーストフードや加工食品を多く摂取する人は、亜鉛不足になりやすいので注意が必要です。また、アルコールを多く呑む人も亜鉛不足になりやすいです。
若くて新型コロナに感染して発病する場合、もしかしたら亜鉛不足が背景に隠れているかもしれません。つまり、コロナ後遺症の人に亜鉛不足が多いということですが、元々亜鉛不足がある人が免疫力低下のため若くして、新型コロナを発症したという可能性があります。
亜鉛は牡蠣(かき)に豊富に含まれているほか、肉類や魚介類、豆類、種実類など多くの食品に含まれています。
糖質制限食の立場で、魚介類や肉類など動物性蛋白質をしっかり摂取すれば、血糖値も上昇しないし、亜鉛も補充できるし、筋力低下予防にもなるし、一石三鳥です。
江部康二
以上引用終わり
今週のお知らせは藤川徳美先生への患者さんからの手紙です。非常に感動的な手紙でしたので、私が文字起こしをしました。是非読んでください。
以下引用始め
NEW!2025-06-13 07:53:21
テーマ:
手紙を頂きました~産後うつ病からの回復~
菜食を10年、→最重度タンパク不足で、プロテインを上手く消化できない、→5g*4など少量頻回服用、→数ヶ月継続すると消化能力が上がり、10g*4が飲めるようになる、→ナイアシンアミド、Mg等の効果を実感できる。
以下文字起こしの手紙の文章です。
藤川徳美先生
はじめまして。○○に住んでおります。○○と申します。元看護士・保健師です。今回藤川先生にお礼とお伝えしたいことがあり、お手紙を書かせていただきました。私自身、長年のうつ病を抱えておりましたが、藤川先生のお陰で克服しております。そして、現在は自身のうつ病経験と栄養の知識を踏まえて、メンタル不調の方の支援を行っております。
先生のお時間を頂戴してしまい大変恐縮ですが、私の回復までの経過と、私が支援させていただいた方々のうれしい変化をお伝えさせていただきたいと思います。
私は大学卒業後、○○の大学病院の集中治療室に勤務しましたが、社会人2年目の2010年に職場のハラスメントをきっかけにうつ病を発症しました。その職場は退職し、1年ほどの無職の期間を経て別の大学病院の集中治療室に就職できたのですが、その後もよくなったり悪くなったりを繰り返しておりました。
「なんで私はこんなに生きずらいんだろう・・・。私は何がおかしいのだろう・・・。」
常にこのような思いを抱えていた中で出会ったのが、夫がたまたま本屋で買ってきた「うつ・パニックは「鉄」不足が原因だった」でした。この本に出合ってから、メンタルと栄養の関係性について意識するようになりました。うつ病を発症してから8年経過した、2018年です。
ただ、実は私はうつ病になった2010年に分子栄養学に出会っています。うつ病になって最初に通った心療内科が、当時珍しかった栄養療法を行っていたのです。休職して実家に戻ってきた際、私は母に「向精神薬は怖い」と話していたそうで、母が薬に頼らない病院を探して通わせてくれました。
先生もご存じの通り、栄養療法をやっている病院は高額な医療用サプリを患者さんに出していることが多く、この病院でも同じく医療用サプリが出されていたのですが、両親は私が良くなるのであればと、高額サプリの費用もすべて出してくれていました。
しかし、サプリを飲み続けることが出来ず、一向に良くなりませんでした。今となってよくならなかった理由がはっきりと分かります。藤川先生が仰っている通り、ベースに重度の低タンパクがあったことにより、体がサプリを受け付けず、また、サプリの十分な効果が得られなかったのだと。
藤川先生の本と出合った同時期に、元から興味のあった栄養学について本格的に学びたいと言う思いから、溝口徹先生が代表理事をされているオーソモレキュラーの団体で学ぶようになり、資格を取りました。
栄養と心身の健康の関係性について学び、食を改善していったことでだいぶ元気になり、もう大丈夫だと思っていたのですが、元気になった1年後の妊娠・出産を経て、今度は産後うつ状態になってしまいました。
赤ちゃんの息子は火が付いたように1日中激しく泣き、私も余裕が全くなく、とにかく「消えたい」「楽になりたい」と毎日思っていました。泣きながら地域の子どもセンターへ助けを求めたこともあります。
でも、助けを求めた子どもセンターでかけられた言葉は「お母さんがどんと構えていればいいのよ」と言われるだけで、”自分が悪い“という偏った思考がどんどん強くなっていく一方でした。苦しいが故に夫に当たり散らし、息子にも愛着が持てず、そんな自分を責め・・。必死に心理カウンセリングを受け続けても状況は変わらず、絶望して命を絶とうとしたことは何度もあります。
もちろん、栄養も必死に取り組んでいましたが、状態は全く改善しませんでした。ただ、それは藤川先生の理論通りに実践していなかったから、また、焦り過ぎていたことが原因だったと思います。日本のオーソモレキュラーではタンパク質の重要性は伝えていても、プロテインを勧めてはいません。そのため、私は食事でタンパク質をかなり増やしていましたが、プロテインは飲んでいませんでした。また、私は学生時代から10年ほど菜食をしており、常にダイエットを意識していたので、最重度の栄養失調があったと言えます。そして、出産で大量出血もしたので、栄養療法に取り組んだからと言って、すぐにはよくならなかったのは当然だったのだと思います。
私も先生の患者さんと同じく「こんなに頑張っているのに良くならない」「変わらない」と、ツイッターで得た情報から様々なサプリに手を出したりしていました。
プロテインも徐々に増やすのではなく、お腹の不調があるのに無理して多く飲んでいたり、腸の炎症があるからと言う理由で鉄サプリを飲まず、別のサプリを摂っていたり、先生が仰っている「焦りまくって治らない」パターンでした。
「治らない」負のループから抜け出せたのは、改めてプロテインの量を少量から始めて、鉄とナイアシンアミドを継続して飲んでしばらく経ってからです。とにかく続けることだけを考え、私だけでなく、夫と息子、家族3人で取り組みました。先生の理論通りに始めてから3ヶ月経過したころ、当時3歳だった息子はひどい癇癪が落ち着きました。それまでは癇癪がひどくて遠出も難しかったのですが、3人で楽しく外出するようになりました。近所に住む義母も「気質が変わったよね」と驚いていたほどです。
私の場合は中学生の頃から腸の状態が非常に悪く、鉄も1日1カプセルからなかなか増やせなかったので、精神的に落ち着くまでに1年以上かかりましたが、希死念慮や家族にイライラをぶつけることがだんだんと減って言った感じです。
やはり先生がおっしゃるとおり、年齢が若いと改善が早く、長年の重度の栄養失調がある場合は改善までに時間がかかると言うことを強く感じました。そして、栄養不足があると焦り過ぎて回復が遠ざかって阿しまう傾向があること、プロテインでベースを作ることがいかに重要かを実感しました。
私は失敗を繰り返していたので、栄養療法に取り組んでからも完全な回復までに数年かかりましたが、私が支援させていただいた方々は藤川先生の理論通りに行っていただき、半年かからず治っている方が多いです。うつ病で失意のどん底であった方が、依然楽しんでいたスポーツが出来るようになり、人生が大きく変わったとおっしゃっていました。
うつ病で休職されていた方が、ワンオペ育児をしながら復職でき、家族との関係性が良くなったと言う方もおられます。また、癇癪のひどい、偏食があるお子さんは1~2ヶ月くらいで改善していますし、1年間引きこもりだった学生が3ヶ月ほどで遠出が出来るようになり、アルバイトも自ら始めて青春を楽しんでいるとのご報告もいただきました。
その他、ご年齢が60~70代の方でも数カ月で長年の不調が改善されています。私の78歳の母も3年前に脳梗塞を発症し、右半身麻痺がありましたが、退院後から食事改善をしてプロテインを飲み続けていることで、全く動かなかった右手が年々動くようになっています。
リハビリでの回復のピークは発症から3ヵ月と言われますが、母は3カ月過ぎてからの方が動くようになっています。(発症当時はコロナの真っ最中で、3カ月の入院中はプロテインの持ち込みなど一切禁止されていました。)字を書くなどの細かい作業はまだ出来ないものの、麻痺がある右手で重いものも持てるほどに回復しています。
このように、私を含め、多くの方々が藤川先生に救われています。藤川先生と三石先生には感謝が尽きません。本当にありがとうございます。先生方への敬意をこめて、今、私は先生の理論を広める活動をしています。それは、この根本的に治す方法で日本人が心身ともに元気になり、日本が変わっていくと確信しているからです。
大げさと思われる子も知れませんが、日本人が本来持っている素晴らしい精神を取り戻していけば、世の中が変わると本気で思っています。先生がご指摘されているように、現在の日本は人口が減る一方で、心身の不調をきたす人は増え続け、子どもの発達の問題も深刻です。国は発達障害が増加している原因を社会の認知や理解が広がったためなどと言っていますが、そうではありません。
長年子どもたちと関わってきた幼稚園や保育園、小学校の先生方に昔と今の子供たちについてお聞きしたことがあるのですが、全員「明らかに昔と子どもが違う」とおっしゃっていました。栄養を満たしていくと子供たちは明らかに良い状態に変化していますから、藤川先生がおっしゃっている通り、栄養不足の影響は非常に大きいと言えます。
これをもっと教育現場で知ってもらう必要があると思いますし、日本社会全体がこの質的栄養失調の問題に取り組むことで、日本が明るく元気になっていくと思うのです。今の日本は不平・不満に満ちていますが、世の中を変えるのは政治ではなく、日本人一人一人の意識と行動。私はこのように思っています。
一人一人が自分で考え、行動できるようになれば、必ず日本は良い方向に変わっていく。そう信じて、地道な方法ではありますが、藤川先生の理論を知ってもらえるような活動を試行錯誤しながら続けていきます。
最後となりますが、いつか、藤川先生にお目にかかりたいと思っております。直接お礼をお伝えするとともに、うれしいご報告が出来ればと。藤川先生と三石先生に敬意をこめて。
○○○○
以上引用終わり
今週のお知らせはまたまた栄養の話です。最近本を何冊か買いましたが、ついつい栄養の本を読んでしまい、歴史や経済の本が後回しになります。
骨粗しょう症はホルモンの関係で中年以降の女性に多く、当院でも大変多いです。骨粗しょう症の薬は炎症や抜歯が引き金になって、あごの骨が腐ることがあるので歯科医は難しい対応を迫られることがあります。
私の母も晩年自分の部屋の電気コードに足を取られ転倒し大腿骨を骨折しました。手術をしましたが正座が出来なくなったり、歩くスピードが遅くなって人と合わせるのが大変だとこぼしていました。
薬もいろんな種類がありますが副作用のことを考えると、出来れば薬を飲まないで食事で対応出来たらそれが一番いいです。
以下引用始め
牛乳はむしろ骨折リスクを上げる…管理栄養士が「丈夫な骨のためにはコレ」と断言する日本人が大好きな食べ物牛乳瓶1本分には角砂糖2個分の乳糖が入っている
60歳から丈夫な骨のために、摂取すべき食材は何か。管理栄養士の大柳珠美さんは「60歳以降の食事や運動、生活習慣によって骨粗鬆症のリスクが上がる。立ち上がるときなどに背中や腰が痛む際は要注意だ」という――。
骨のなかでは古くなった骨が吸収される「骨吸収」と、新しい骨が形成される「骨形成」が繰り返されています。骨吸収と骨形成のバランスが崩れ、骨吸収が進んでしまうと骨量が減って骨がスカスカになる「骨粗鬆症」となり、転倒などで骨折しやすくなってしまいます。
骨折しやすいのは背骨、手首、大腿骨頸部(だいたいこつけいぶ)(太ももの付け根)。大腿骨頸部の骨折は入院手術が必要になり、寝たきりや認知症につながるおそれもあります。
自覚症状がないまま静かに進行し、骨折してはじめて気がつくケースがほとんどですが、軽度から重度では次のような症状が見られます。
○骨粗鬆症の症状(軽度→重度)
□立ち上がるときなどに背中や腰が痛む。→背中や腰が激しく痛み寝込む。
□重いものを持つと背中や腰が痛む。→転んだだけで骨折する。
□背中や腰が曲がってくる。→背中や腰の曲がり方がひどくなる。
□身長が縮んでくる。→身長の縮みがかなり目立つようになる。
骨量は20歳前後をピークにどんどん低下していきます。女性ホルモンのエストロゲンは骨形成を促し骨吸収を抑える働きがあるため、閉経後の50代から女性は骨量が減少して骨粗鬆症のリスクが上がります。
男性は女性に比べて骨が太く丈夫なため骨量もみっしりとあり、女性のようにホルモンの急激な変化にさらされることはありませんが、60歳以降の食事や運動、生活習慣によってそのリスクが上昇します。
男女ともに栄養面ではタンパク質、カルシウム、マグネシウム、ビタミンD、ビタミンKの不足が原因となります。
さて、骨粗鬆症といえば「カルシウム」、カルシウムといえば「牛乳」とばかりに、骨粗鬆症対策で牛乳を常飲している方は多いと思いますが、気になる研究報告もあります。アメリカのメリーランド大学の調査では、牛乳の摂取量が多いほど骨折率が高いという結果が出たそうです。
1946年から2021年までの観察データを解析したところ、牛乳の摂取と大腿骨骨折には関連が見られませんでした。牛乳をまったく飲まない人と比較したところ、骨折リスクが最も高かったのは1日400gを摂取する人で、リスクは15%も高かったそうです。もう少し詳しく見てみましょう。
・牛乳の摂取量が1日400gまでの場合
→骨折リスクは200g上昇するごとに7%上昇。
・牛乳の摂取量が1日400gを超えた場合
→まったく飲まない群と比較すると700gに達するまでリスクは上昇する。
ただし、ヨーグルトと発酵乳、チーズについては逆の結果になっています。
・ヨーグルトと発酵乳の1日の摂取量が250g増加するごとに
→骨折リスクは15%低下。
・チーズの1日の摂取量が43g増加するごとに
→骨折リスクは19%低下。
乳製品を何代にもわたって摂取し続けてきたアメリカでの調査結果ですから日本人にピッタリ重なるとは限りませんが、そもそも日本人は牛乳に含まれる乳糖を分解する酵素を持たない人が多いのです。
牛乳を飲む歴史が浅い日本では乳糖分解酵素という仕事人が必要ありませんでした。仕事人なしに牛乳を飲んでも有効活用は難しく、お腹がゴロゴロするだけの牛乳に健康効果があるのかというと疑問符がつくところ。
「お腹がゴロゴロしないなら、カルシウム補給のために牛乳を飲んだほうがいいんじゃないの?」と思う方もいるかもしれませんが、ここにも問題があります。
牛乳だけを飲んでもマグネシウムがないことには骨を構成することはできず、カルシウムしかない牛乳を体に入れ続けると、マグネシウムが足りなくなってしまいます。
筋肉の働きに関わるマグネシウムの不足で筋肉がつる(こむらがえり)などはまだマシで、不整脈や心筋梗塞を起こし、極端な状態では心臓が止まることさえありうるのです。
では、骨を丈夫にするためのカルシウムは何から摂ればいいのか? イワシの丸干しや出汁(だし)をとる煮干しなどの骨ごと食べられる魚、また、海藻や大豆製品もよいでしょう。これらはカルシウムとマグネシウムが両方入っているからです。
これらの食材は、いずれも和食ではお馴染(なじ)みのものばかりです。やはり、日本人の健康のためには何世代にもわたって食べられてきた伝統的な和食が最適といえます。
さて、カルシウムとマグネシウムのように、ペアとなって働くミネラル同士を「ブラザーイオン」といいます。銅と亜鉛、カリウムとナトリウムなどもブラザーイオンです。
ミネラルには体にマイナスとなる「有害ミネラル」も存在し、体のなかの必須ミネラルは有害ミネラルの排出にも作用します。共に協力する「ブラザーイオン」だけでなく、有害ミネラルとそれらを排出するミネラルも、ある意味、「セットで働く(反応する)」といえるでしょう。
共に働く仲間があぶれることのないよう、また有害ミネラルの排出のためにも、ミネラルという仕事人をバランスよく多数そろえておくことは重要なのです。
丈夫な骨をつくるために牛乳がプラスにならないのは、骨をつくるために必要な栄養素がそろっていないからです。栄養素は単体で働くのではなく互いに作用しながら力を発揮します。骨をつくるために必要な栄養素には次のようなものがあります。
摂取したタンパク質は分解合成されてコラーゲンとなり、血管、臓器、皮膚、そして骨とあらゆるところで利用されます。骨の主成分はコラーゲンであり、その材料のタンパク質は丈夫な骨をつくるために必須です。
前述のようにカルシウムのブラザーイオンとして、カルシウムとともに骨や歯の構成成分となり、骨の代謝を正常に保つ働きがあります。ストレスが多いと尿となって排泄されてしまうので、大豆製品、海藻、小豆(あずき)などで補充しましょう。
リンはカルシウムの次に体内に多く存在するミネラルで、カルシウムやマグネシウムと結びついて骨や歯をつくっています。一般的な食生活を送っていれば不足することはありませんが、ビタミンDの不足、栄養不良、薬剤の使用などの影響で利用率が低下することがあります。
骨はコラーゲンを主成分として、カルシウムとリン酸、そしてマグネシウムでできています。亜鉛はビタミンCとともにコラーゲンの生成に必要です。
タンパク質と結びついて各臓器に存在し、カルシウムの代謝・骨の成長に関わり、関節の軟骨を守る効果も期待されています。鶏皮、鶏の軟骨、牛、豚のほか、納豆やオクラといったネバネバ食品に多く含まれます。真皮のコラーゲン層を丈夫にすることから肌にもプラスになると考えられています。
骨の主成分となるコラーゲンの合成に働きます。骨のほか、血管、皮膚、粘膜のコラーゲン形成にも関わっています。白血球を活性化させるので、風邪や感染症の際には免疫力を上げるためビタミンCを積極的に補給しましょう。
カルシウムやリンの吸収を促進して骨量を保ち、折れにくい骨をつくります。補充に最適なのは「魚」です。
骨へのカルシウムの取り込みを助けて石灰化を促すほか、骨からのカルシウムの流出を抑制してしっかりした骨づくりをサポート。納豆、海苔、ワカメに多く含まれます。抗生物質の長期服用でビタミンKを活性化させる酵素の働きが低下することがあります。
コラーゲン繊維を規則正しく配列して適度な弾力を保ちます。
骨粗鬆症のリスクを計る指標のひとつに「骨密度」があります。骨密度検査とは骨を構成するカルシウム、リン、マグネシウムなどのミネラル成分がどれだけ骨に詰まっているかを調べるものです。
骨密度が高いほどミネラルが詰まっているので丈夫な骨のようですが、それでも骨折するケースがあります。実は、骨の強度を決めるのは骨密度と「骨質」です。では、骨質とはなんでしょうか?
それがコラーゲンです。
骨を鉄筋コンクリートの建物だと考えてみましょう。鉄筋はコラーゲン、コンクリートはカルシウムなどのミネラルにあたり、鉄筋とコンクリートがしっかりしていないと建物の強度は保てません。
骨密度(コンクリート)が詰まっていても、鉄筋であるコラーゲンの質が悪ければ骨折だって起こります。骨の強度は骨密度70%、骨質30%で決まるといわれているのです。
鉄筋であるコラーゲンはタンパク質なので、体内の糖と結びつくと糖化を起こし弱体化します。ミネラルが詰まって骨密度が高くても、コラーゲンが糖化してしまうと骨の強度は低下し、骨折リスクを負うことになるのです。
さて、ここで牛乳の話に戻りましょう。牛乳はカルシウムは豊富でも、カルシウムと結合するマグネシウムを含んでいないため、骨密度を上げず骨粗鬆症予防にはならないと説明しました。
もうひとつの牛乳のデメリットが乳糖です。牛乳瓶1本分の乳糖は角砂糖2個分にあたります。つまり、体内の糖化を進めるおそれがあるのです。「骨粗鬆症予防に牛乳」と信じて常飲していると骨の劣化をもたらしかねません。
反対に、乳糖も含めた糖質を制限することはコラーゲンの糖化を抑え、骨粗鬆症予防にもつながるといえます。
【まとめ】60歳から丈夫な骨のために「牛乳」よりも「豆腐とワカメのみそ汁」を
□牛乳は骨をカルシウムとともに働くマグネシウムがない。
□カルシウムなどのミネラルを増やしながら、コラーゲンをしっかりつくって骨質を上げることも大事。
□骨を強くする栄養素が豊富な和の食材を活用。出汁に使った煮干しも一緒に摂れる「豆腐とワカメのみそ汁」はおすすめ。
以上引用終わり
人の体は複雑で不思議です。まだまだ判らない事だらけです。
以前読んだ本では、小脳変性症の女性が病気を克服するために辿り着いた食事が「青汁」だったと言うので驚いたことがありました。人の一番大事なタンパク質をどうやってとっているのか不思議でしたが、彼女の腸内細菌を調べたら「草食動物」のような腸内細菌だったそうです。腸内細菌がタンパク質を作ってくれている牛や馬と同じです。
また、マツコ・デラックスの番組で10年近く果物だけを食べている男性が出演して、血液検査でも問題は無く骨も丈夫だったそうです。私は十数年前「糖質制限」に出会い何冊も本を読んで実行に移し現在の健康に辿り着きました。健康への道は行く筋もあるようです。
今回は果物についてのお話です。
以下引用始め
5/19(月) 10:02配信
高齢者が突然の骨折により、歩けなくなったり寝たきりになってしまう――このような危険な骨折は「骨卒中」と呼ばれています。食事を変えて骨を強くするにはどうすればいいのか、『栄養整形外科医の 一生折れない骨をつくる「強骨みそ汁」』より一部抜粋・再構成のうえお届けします。
■骨折した高齢者の骨に起きていること
骨折を予防するうえで控えていただきたいものがあります。それが「糖質」です。改めて説明すると、三大エネルギーであるたんぱく質、脂質、炭水化物のうち、炭水化物から食物繊維を除いたものが糖質です。
糖質の問題点については、ここ数年で多くの人に理解されるようになりました。糖質の摂りすぎは、糖尿病だけでなく、肥満や老化を招きます。さらには、骨の質を低下させることもわかってきたのです。骨の原料としてはコラーゲン(たんぱく質+鉄+ビタミンC)が重要ですが、そのコラーゲンを変質させてしまうのが「糖化(グリケーション)」という現象です。糖化は、糖質(ブドウ糖、果糖)の摂りすぎによって起こります。食事を通して体内に取り込まれた糖質は、消化・吸収を経て、血糖となって血液中に出てきます。これを測ったものが血糖値です。
食事を摂れば血糖値は上がるものですが、体にとっては血糖値の変動が少ないほうがいいのです。そのため、体にはインスリンというホルモンを出して、血糖値を下げる働きが備わっています。しかし、糖質を摂りすぎていると、この血糖値の調節がうまくいかず、高血糖状態が続いてしまうのです。それが常態化したのが糖尿病ですが、糖尿病でない人でも、糖質の摂りすぎで体のなかで糖を余らせてしまっている人は少なくありません。
この体内の余った糖質がたんぱく質と結びつくと、AGEs(エイジズ)(糖化最終産物)という老化物質をつくり出してしまいます。AGEsは分解されにくく、体の組織に蓄積されて、さまざまな悪さをします。例えば、血管にくっつけば動脈硬化の引き金になり、皮膚にたまればシワやたるみの原因となります。もちろん、骨も例外ではありません。糖化が起きた骨は黄褐色(おうかっしょく)に変色し、脆くなります。正常な骨は白い色をしていますが、それが黄褐色になってしまうのです。
かつて手術をした際には、そんな糖化した骨をよく見たものです。高齢者の背骨の手術で、肋骨を取って移植したことがありました。その肋骨が黄褐色に変色していたのです。今なら明らかに糖化の影響だとわかりますが、栄養療法を知らなかった当時は、その問題点を意識することはありませんでした。腱にも糖化による変色が起こります。指の腱鞘炎が進むと「ばね指」といって、曲げた指を伸ばそうとしたときに、バネのようにピンと跳ね上がるようになります。その手術をしたとき、やはり、高齢者の腱が黄褐色を帯びていました。
先ほど筋肉や骨の原料を確保することの重要性を述べましたが、もう1つ重要なのは、同時にこの糖化を防ぐ手立てを講じることです。つまり、食生活を見直し、糖質の摂りすぎをやめる。この2つが、「骨卒中」を防ぎ、元気で長生きするポイントなのです。
■果物の糖でも油断は大敵
食に関心が高い高齢者のなかにはご飯やパン、麺類などの糖質を控えているという人がいます。もちろん、好ましい食生活といえますが、それにもかかわらず数値に改善が見られないケースがあります。
クリニックの患者さんにも糖質を控えているのに、中性脂肪の数値が高い人がいました。中性脂肪の材料となるのが余分な糖質ですから、ほかにも何か糖質をたくさん摂っていることが疑われました。しかし、食事内容を聞いても、ご飯、パン、麺類は食べていないし、お酒も飲んでいないという答え。そこで最後にこう聞いてみました。「じゃあ、果物は食べてない?」患者さんは意外そうな表情を浮かべました。「えっ、果物はダメなんですか?」
どうやら果物は制限の埒外に置かれていたようです。実は、このような患者さんはかなり多い。糖質制限をしていても、果物は別物だと思って、健康のためにせっせと食べてしまっているのです。日本では季節ごとにおいしい果物が店頭に並びますから、食欲をそそられるのもわかります。ただ、日本で栽培される果物のなかには、品種改良によって糖度を高めているものがたくさんあります。甘い果物は、もはやお菓子を食べているといっても過言ではありません。この患者さんも毎日トマトジュースを飲み、ご主人ともどもリンゴを朝と晩に食べていました。果糖をどんどん取り込んでいたわけです。
果物や野菜に多く含まれる果糖には、実は血糖値を上げる作用はありません。しかし、その糖化の作用はブドウ糖の何倍もある“曲者”なのです。ちなみに、トマトジュースの場合、メーカーによって差がありますが、1缶に含まれる糖質量は角砂糖2個〜4個半分にも相当します。
■クマは冬眠する前に果物を好んで食べる
この患者さんの中性脂肪を上げたのは、果物の“常食”だったと思われます。最近ではトマトやニンジンなど、野菜のなかにも糖度の高いものがあります。中性脂肪が高い患者さんのなかには、果物も減らしたのになかなか中性脂肪が下がらない方がいますが、問診したところトマトをたくさん食べていた、というケースもありました。
私は患者さんに果物の話をするとき、しばしばクマを引き合いに出します。クマは冬眠する前におなかにたっぷり食べ物を詰め込みます。果物も大好物です。なぜ、そうするのか。冬眠に備えて皮下脂肪(中性脂肪)をつけるためです。果物の果糖はそのうえで大きな役割を担っています。クマは必要にかられてそうしているわけですが、冬眠をしない私たちにその必要はありませんよね。糖質を減らすという観点からいえば、果物は注意すべき食品といえます。とくに甘い(おいしい)果物はできるだけ控えるべきでしょう。果物を食べるなら、びわ、キウイ、グレープフルーツ、はっさくなどの柑橘類、つまり、甘さが“物足りない”もの、酸味が強いものがおすすめです。
「果物=健康食」という刷り込みもあって、果物に含まれる果糖の問題点(糖化や中性脂肪の増加)は、案外盲点になっているのかもしれません。甘くておいしい果物の摂りすぎには十分注意するようにしてください。
大友 通明 :医療法人社団二柚会理事長、大友外科整形外科院長
以上引用終わり
むし歯は無いのに歯がしみることがあります。歯冠は通常エナメル質でおおわれています。エナメル質は神経とつながっていないので感覚が無く物を噛んでも痛くありません。歯磨きを力いっぱいしていると、歯肉が下がって歯根が露出してきます。歯根は象牙質と言って神経とつながっている組織なので触るとピリッと痛んだり冷水がしみたりします。これを知覚過敏と言います。シミ止めを塗ったり知覚過敏用の歯磨剤を使用していると改善します。
しかしながら、食いしばりや歯ぎしりなどで歯の神経が過敏になってしみている場合は別の治療法が必要になってきます。例えばマウスピース装着やビタミンB3(ナイアシンアミド)のサプリメントを摂ることになります。
今回はナイアシンアミドに焦点を当てることにします。
まず、分子栄養学、オーソモレキュラー栄養学を研究している藤川徳美先生のブログ「精神科医こてつ名誉院長のブログ」から転載します。
以下引用始め
ビタミンB3服用の際の注意点
ビタミンB3には、
1)(フラッシュタイプ)ナイアシン、
2)フラッシュフリーナイアシン(ノンフラッシュナイアシン)、
3)ナイアシンアミド、の3種類がある。
統合失調症、躁うつ病、自閉症や知的障害の情緒障害、うつ病、パニック障害、リウマチなどを改善させる効果がある。用量は6歳までは1500mg程度、7歳以上は3000mg程度。
効果の強さは、1)>2)>3)だが、いきなり(フラッシュタイプ)ナイアシンを服用すると激しいナイアシンフラッシュが出るため、必ずナイアシンアミドで開始する。
*ナイアシンフラッシュとは、服用1時間後に末梢血管拡張作用、ヒスタミン放出作用により発赤、痒みが出る。正常な生理反応で危険なものではない。継続服用することによりフラッシュは徐々に軽くなり、出なくなる。
1)ナイアシンアミド
フラッシュは出ないので、500mg*3(朝昼夕それぞれ1,1,1)で開始して、一週間後500mg*6(2,2,2)に増量する。吐き気、眠気が出たら減量する。カプセルが飲めないお子さんは、カプセルの中身を出して他のものに混ぜて飲ませる。ただし、かなり苦いので元々苦いココア、チョコアイス、チョコプロテイン、ミロなどに混ぜる。
2)フラッシュフリーナイアシン(ノンフラッシュナイアシン)
1錠640mgのフラッシュフリーナイアシン+160mgのイノシトールを含有している。6歳以下なら2カプセル(朝1+夕1)、7歳以上は4カプセル(朝2+夕2)程度。カプセルが飲めないお子さんは、カプセルの中身を出して他のものに混ぜて飲ませる。無味なのでヨーグルトなどに混ぜる。フラッシュフリーでも、人によればフラッシュが出ることがある。継続服用することによりフラッシュは徐々に軽くなり、出なくなる。
3)(フラッシュタイプ)ナイアシン
3ヶ月間ナイアシンアミド、もしくはフラッシュフリーナイアシンを継続しても効果が不十分な場合、ナイアシンに変更してゆく。
*ただしこのものは、統合失調症、躁うつ病以外の患者には推奨していない。
*ナイアシン類はネットで購入可能。
「iHerb」https://jp.iherb.com/
紹介コード「JZD352」を利用すると5%引きになる。
以下引用終わり
調べてみると、知覚過敏に対してナイアシンアミドを一日三回、食後に飲んで2~3日で改善する場合もあるようです。
ナイアシンは血糖値を安定化させ、筋肉や過緊張を緩和します。酸化ストレス(シミ・しわ・白髪などの老化原因の一つ)を軽減させます。血糖が上がるとアドレナリンが分泌され筋肉が緊張することによってブラキシズム(夜間のくいしばり、歯ぎしり)が起こると言われています。
この他にもナイアシンは、神経の働きを安定化させるため、寝つきが良くなったり、皮膚や粘膜を正常化させるため、メラニンの生成も抑え、シミ・そばかすを減らす効果もあります。
アルコールの代謝も助けるため、アルコールを飲んだ後に飲むと二日酔いが軽減されます!是非試してみて下さい。
藤川徳美先生の「若さを保つ栄養メソッド」 より
以下引用始め
NEW!2025-02-15 07:21:42
テーマ:
カルシウムが蓄積して起こる痛み
「若さを保つ栄養メソッド」 より
カルシウムとマグネシウムのバランスが悪くなると、さまざまな症状が出てきます。尿路結石、腎結石は耐えがたいほどの痛みをともなう病気ですが、これもカルシウム過剰かつマグネシウム不足が原因です。
結石はシュウ酸とカルシウムが結合してつくられます。マグネシウムは結石の生成を抑制する働きを持っているのですが、これが不足すると結石の生成が進んでしまうのです。そのため結石の予防や治療薬として、マグネシウム製剤が使われています。
結石については、かつてビタミンCの摂り過ぎが原因などといわれていました。ビタミンCを摂ると代謝産物の一部であるシュウ酸が尿中に増えることから、勘違いが起きていました。実際は尿中のカルシウムはビタミンCと結合しますので、シュウ酸と結合するカルシウムの量は減少することとなります。ビタミンCはむしろ結石生成のリスクを減らしていたのです。
肩関節石灰沈着症 またカルシウム過剰によって痛みが起きる、肩関節石灰沈着症という症状があります。中高年の方に多い症状で、肩などに急激な痛みを感じて、「肩こりか、五十肩か」と整形外科を受診されます。病院では痛み止めの注射、鎮痛剤や湿布をもらうだけで、なかなか改善しません。あるいは病院で首を伸ばすストレッチをしたり、患部を温めたりしても、なかなか治らないのが現状でしょう。こうした痛みもマグネシウム不足が原因です。
骨の中では必要なカルシウムを維持するため、血中にもカルシウム濃度を保とうとする働きがあります。不要なカルシウムは尿とともに排出されるのですが、年齢とともに尿から排出しきれなかったカルシウムが、血管壁や関節内の腱、靭帯などに蓄積してしまうのです。
蓄積されるだけなら痛みはありませんが、些細なことをきっかけに異物反応が発生すると、体の防衛機能でカルシウムを一挙に攻撃し、関節内では炎症による激痛が発生してしまいます。
サプリメントでマグネシウムをしっかり摂り、痛い部分に塩化マグネシウムを擦り込んでみてください。とくに経皮から吸収されたマグネシウムは沈着したカルシウムを取り去ってくれるため、痛みが和らいていきます。患部に直接擦り込むことで、即効性も期待できます。痛み止めを飲んでやり過ごしていても、何の改善もしませんし、鎮痛剤の種類によっては胃腸を悪くします。
高血圧や動脈硬化 カルシウムの沈着が血管壁で起こるとどうなるでしょうか。血管が固くなり、高血圧や動脈硬化の原因になります。マグネシウムは高血圧や動脈硬化の予防にもなるのです。
偏頭痛 また、偏頭痛もカルシウムイオンが血管の収縮を強くしていることが原因のひとつです。偏頭痛の予防と治療にはマグネシウムが有効です。もし偏頭痛の発作が起きたら、早めにマグネシウムのサプリメントを摂取し、痛い部分を冷やしながら安静にすることで痛みが治まります。
こむら返り そして、ふくらはぎの筋肉が激しく収縮を起こす、こむら返り。あの激痛は耐えがたいものですが、こむら返りの原因もミネラルバランスが関係しています。血管と同じく筋肉においても、カルシウムは収縮、マグネシウムはその調整と弛緩の役割を担っています。
双方のバランスが取れてはじめて、筋肉をスムーズに動かすことができます。しかし体内に蓄えられている量は、カルシウムがマグネシウムより圧倒的に多いため、発汗などによってミネラルが失われると、すぐにマグネシウムが不足することになり、筋肉が収縮から回復できず「足がつる」状態になってしまうのです。
スポーツ好きでよく汗をかく人、汗かきの人、ミネラルの消化吸収が低下している高齢者は、マグネシウムが不足しがちです。
カルシウムが蓄積されるからといって、何もカルシウムの摂取を極端に制限する必要はありません。本書ではあえて強調していませんが、必要なミネラルです。日本ではカルシウムの重要性は十分に認識されていると思いますし、習慣として意識されている人も多いでしょう。実際に十分摂れている人は、少なくありません。ただしカルシウムだけを摂るのではなく、マグネシウムとのバランスを考えて摂取してください。
また、カルシウム過剰は摂り過ぎから起きるのではなく、カルシウム摂取が少なすぎるために起きることもあります。これは「カルシウムパラドックス」といわれる現象で、カルシウム摂取が少ないと、骨からカルシウムが溶け出して血中のカルシウムが過剰になってしまうのです。
カルシウムを丈夫な骨に役立てるためには、まずはマグネシウムです。そして、マンガン、ビタミンDも摂取できれば御の字です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Mg不足があるとCaを溶解状態に維持できない。つまり、異所性Ca沈着を生じる。動脈硬化、弁膜症、脊柱管狭窄症、白内障など、Ca沈着をする疾患は全てこれが原因。
真夏のJリーグ、Jリーガーが後半になると足が攣るのも、Mg不足が原因。汗からMgが排出され、体内がCa過多となっている。ハーフタイムに、下肢にMgスプレー、もしくは塩化Mg飽和液を塗布すれば、予防できる。
元記事はこちら
https://www.facebook.com/share/15fQJWT2bh/
以上引用終わり
上記の他にも、藤川徳美先生は歯磨きに「にがり磨き」を提唱しています。私も歯石が付きやすい患者さんにおすすめしています。実際に歯石は減っています。
私は小さいころから水泳などですぐに足がつっていました。また学生時代に心電図を取った時、正常な心電図とは少し違っていました。その時の主任教授の説明では特に問題ではないと言われました。今考えるとMgをたくさん必要とする体質だったのかも知れません。現在、Mgのサプリメントと塩化マグネシウム(にがり液)スプレーを使用して全身に擦り込んでいます。スポーツあとの痛んだ部位には特に入念に擦り込んでいます。
私は、昨年夏ごろ、歯医者の備後地区同窓会で分子栄養学、オーソモレキュラー栄養学の講演をさせてもらいました。こむら返りに悩まされている後輩歯科医が2名いました。その後、マグネシウムのサプリメントを飲んで、ふくらはぎに塩化マグネシウムをすり込んだら、こむら返りが起きなくなったと喜んでくれました。
二十歳の男性患者さんにニガリの話をしていたところ「私は野球をやっていて足がつった時にはにがりを使っていました」と言われて、すでに活用していることに驚きました。
塩化マグネシウムは「にがり」のことで、福山ではハローズの食塩売り場に100ml入って¥300弱で売っています。困っている方、ぜひやってみて下さい。
ニチガと言う会社では粉末やフレーク状の塩化マグネシウムを売っています。これを水に溶かして使うのがお得ですが、余り量の多いものを買うと全部使いきるまでに湿気を吸ってカチンカチンになって使うときに難儀しますので注意が必要です。
こむら返りには漢方薬の「芍薬甘草湯」服用も効果がありますが、私が試したところ、にがりをすり込む方が効果と即効性で優れていました。
酸化マグネシウムは便秘の時に使います。緩下剤です。多すぎると下痢になりますから量の調節が必要です。マグネシウムのサプリメントでは、下痢になりにくいクエン酸マグネシウム、グリシン酸マグネシウムを摂取します。それでもたくさん飲み過ぎると下痢するのでその一歩手前がその人の上限量になります。
私の知人に肩の手術をされた方がいますが、不整脈もあったので、Ca過多Mg不足であった可能性が高いです。この記事を読んでいる方にはMg摂取をお勧めします。